はじめに
最近、法人研修の現場で感じるのは、「知識を伝える研修」は多いが、「現場を動かす研修」は少ないということです。
研修・教育という言葉には“形だけ”が先行している現場が多い。
実践を変えるためには「会話設計」という視点が必要です。
第一章:従来型の営業研修が成果につながらない理由
一般的な研修は「話し方」「理論」「敬語」「ロープレ」の繰り返し。
しかし、会話は設計できるものであり、「練習量」だけでは改善されない。
形式ではなく、構造を教えなければ人は変わらない。
FABE法やABC理論、プロダクトアウト営業は昔ながらの手法や理論であり、幾ら教えても実践で活かせるケースが少ないのです。
また笑顔を絶やさぬようにと鏡を持って来させた講師もいたが、それはあくまでもインバウンド向きであり、
声が笑顔でいることがかえって相手を怒らせてしまうことにもなりかねません。
それよりも臨機応変に対応ができる順応力を上げるべきだと考えます。
ここでも相手を「読む力」が重要になります。
第二章:会話設計とは何か
テレアポを「設計する」とは、話す順序・目的・反応を仮説化すること。
設計とは「感情の流れ」を読む作業である。
この構造を理解すれば、誰でも“再現できる営業”になる。
やはりここでも相手を「読む力」が重要になります。
本稿で繰り返し触れている「読む力」とは、相手の感情や意図を観察し、言葉の裏側を感じ取る力のことです。
それは、見た目の表情や声のトーンだけでなく、「沈黙の意味」までを読む力だといえます。
第三章:法人研修での実践 ― 咲田メソッドの現場
通話ログを個別に聴き、良い点を先にフィードバック。
改善点を“宿題”として設計化。
その際、単に「こう言いなさい」ではなく「なぜそう感じたか」を対話する。
教えるのではなく、“感じ取る回路”を開かせるのが目的。
たとえば、ある保険系コールセンターの研修では、通話ログを聴く前にまず「どんな相手だったのか」を本人に説明してもらうことから始めます。
その上で、講師が客観的に聴き取り、感じたことを伝えます。
“上から教える”ではなく、“並んで考える”構図をつくることで、アポインターが自分の会話を客観的に見られるようになります。
第四章:研修のゴールは“自走する会話”を作ること
指示ではなく自分で修正できる状態を作る。
ロープレは繰り返しではなく、“設計検証”のために行う。
退屈なロープレで疲弊してしまうアポインターを何人も見てきました。
教わる人が「観察する立場」に立てたとき、会話は変わる。
結論:研修を「会話設計」の時代へ
教育とは、正解を教えることではなく、設計の観点を渡すこと。
テレアポという行為に“デザイン思考”を持ち込むこと。
それが、これからの法人教育が進むべき方向だと考えます。
さらにこれからはカスタマーハラスメント(カスハラ)に合ってしまった場合に、どのように対応するかを示しておく必要があります。
それは研修の一部として、従業員を守る「心理的安全性」の設計でもあります。
コミュニケーション・ラボ
Communication Lab SAKITA
テレアポアーティスト(テレアポ改善コンサルタント) 咲田哲良(さきたあきら)
咲田哲良が扱っている仕事の全体像はこちら
https://sakita.ltd/works/
📩 お問い合わせ・無料相談
個人の方はこちら
法人の方はこちら
関連記事
著者: テレアポアーティスト 咲田哲良(さきたあきら)
営業と教育を「整える力」で再構築する活動を展開中。
SNSでも最新の気づきを発信しています:
X /
note /
LinkedIn
著者プロフィール: テレアポアーティスト(テレアポ改善コンサルタント)咲田哲良のプロフィールはこちら
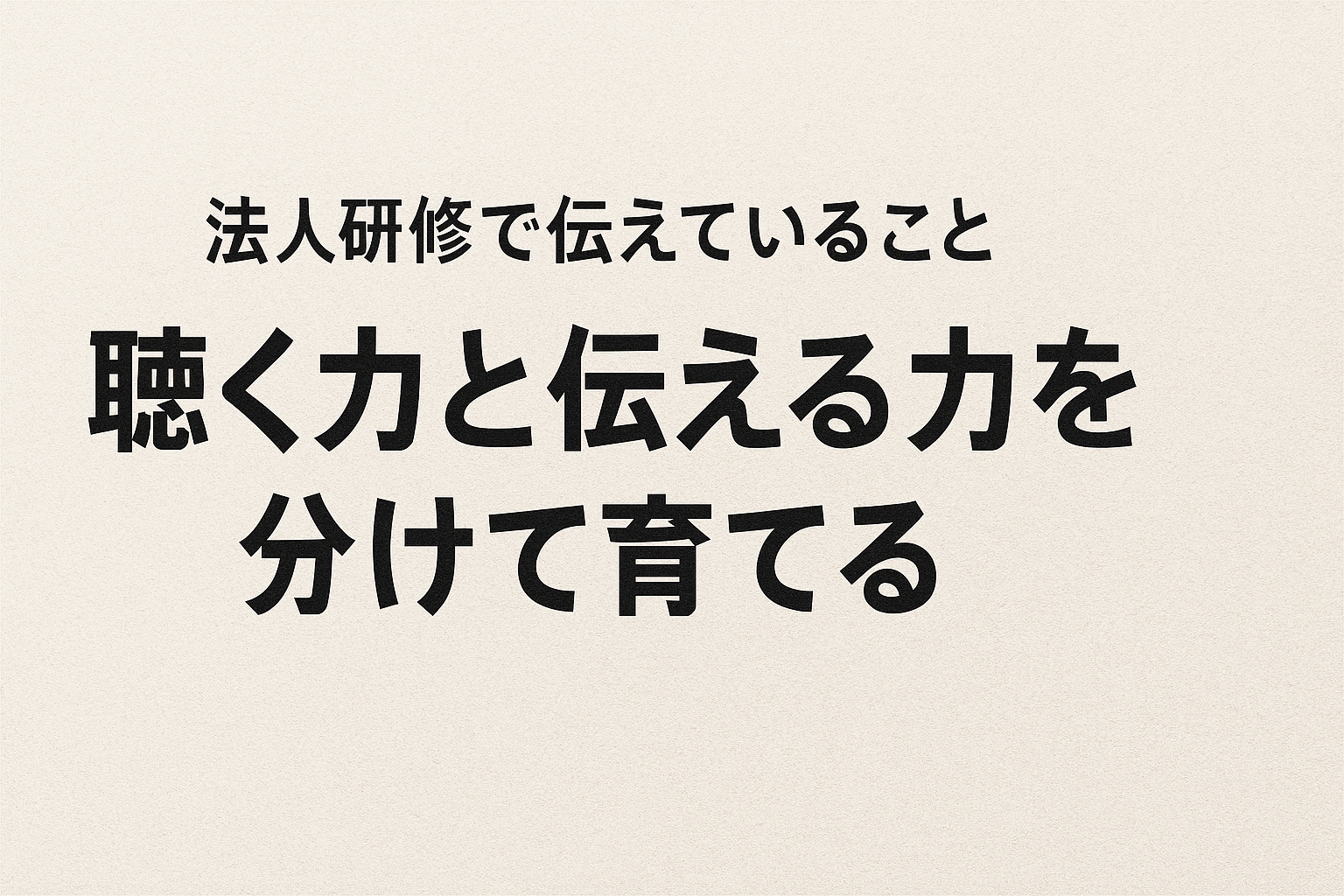
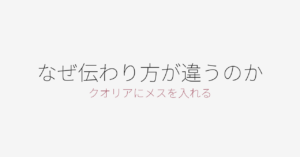
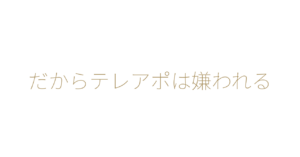
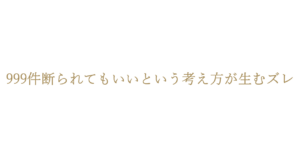
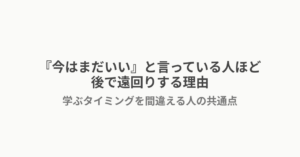
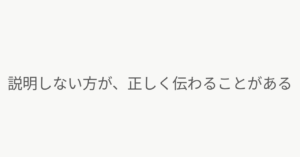
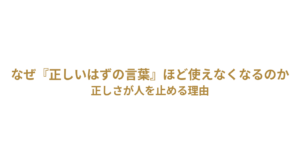
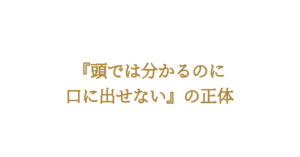

コメント